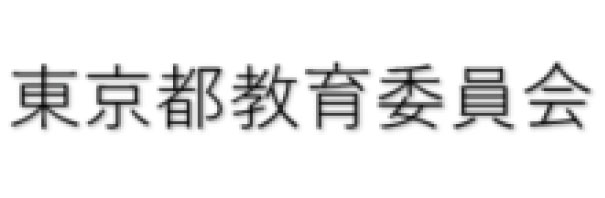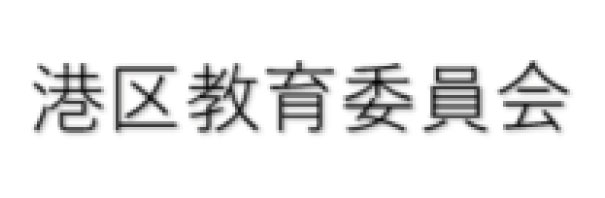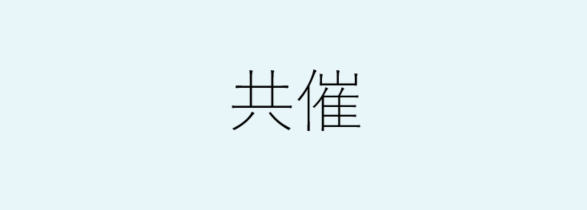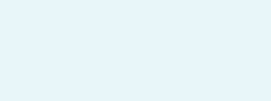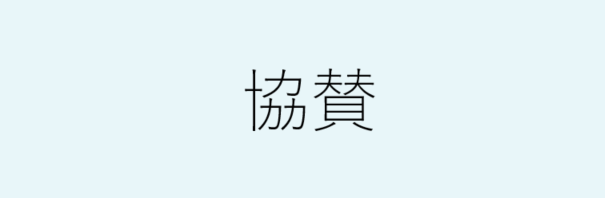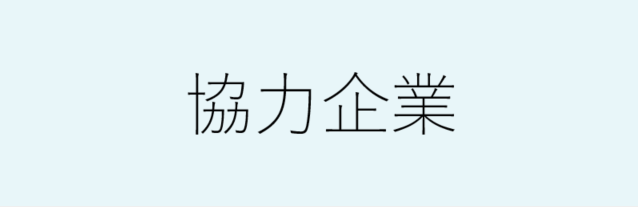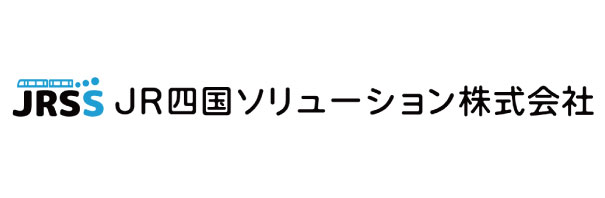【8/1更新】
IMETSフォーラム2025
第51回 教育工学研修中央セミナー
< 研修主題 >
【ICT活用による「深い学び」の実現と「働き方改革」の推進】
会場 :
@港区立小中一貫教育校 赤坂学園 赤坂中学校◆お知らせ◆
無事に終了いたしました。
ご参加いただいた皆様、ご協力くださった関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。
研修会の詳細につきましては、後日あらためてご報告いたします。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
NEWS
お知らせ
ABOUT
IMETS FORUM
IMETS フォーラムとは
IMETSフォーラムは1973年より、文部科学省や東京都教育委員会ほか諸教育関連団体の後援のもと主催しています。 教育工学を中心に、最新の教育テーマを取り入れた実践的な研修は非常に高い評価を受けております。 本フォーラムでは、研修テーマ(主題)を設定しており、その研修主題に示したねらいを達成するために、個人および組織(学校全体)として、今後何を、どのように取り組むべきか、参加者それぞれが主体的に考えるための研修とすることを目指しています。
DATE AND TIME
一部の内容は、順次公開予定です。
※タイムスケジュールには変更が生じる場合がございます。
2025年 7月29日(火)
講演
【基調講演】★動画あり
ICT活用力と自己調整力を育む授業とカリキュラム
/村川 雅弘
講演
【講演】
「新たな教師の学びの姿」の実現に向けた仕組みの構築
/石川 仙太郎
講演
【鼎談】★動画あり
1単位40・45分午前5時間制による特色ある教育活動の実現・自己調整力の育成・働き方改革の推進
/村川 雅弘・玉村 昌彦・相田 宜紀
ワークショップ
【7月29日(午前)】
教育を豊かにするChatGPTを体験しよう/池田 修
※午前・午後で同じ内容です。
ワークショップ
【7月29日(午前)】★動画あり
PBLで探究的な学び&ARの活用事例紹介と少し体験
/矢野 充博
ワークショップ
【7月29日(午前)】★動画あり
トランプゲーム「大富豪(大貧民)」の戦略を考え、プログラミング的思考力を育もう/村川 弘城
ワークショップ
【7月29日(午前)】
学習者自身によるAARサイクルの駆動とICT機器活用
/久保 賢太郎
ワークショップ
【7月29日(午前①・午後②)】
通常の学級に在籍する要支援児
① ~長所活用型指導による支援~
②~心理的疑似体験による理解~
/小林 玄
ワークショップ
【7月29日(午後)】
教育を豊かにするChatGPTを体験しよう/池田 修
※午前・午後で同じ内容です。
ワークショップ
【7月29日(午後)】★動画あり
「深い学び」につなぐ手立てを探る 〜コラボノートを活用して〜
/石堂 裕・村川 弘城
ワークショップ
【7月29日(午後)】
生成AIの活用による校務の効率化と授業改善
/田部 久美子
ワークショップ
【7月29日(午後)】★動画あり
子どもの心とことばを育むコミュニケーションワークショップ ~”プレ思春期”のソーシャルスキルトレーニング~/小寺 絢子
2025年 7月30日(水)
講演
【特別講演】★動画あり
生成AIが変える学校教育の姿
/池田 修
講演
【講演】
データから見る子どもの学びと将来イメージ/川田 夏子
講演
【事例発表】★動画あり
DXの中で大事にしたいこと 〜つくば市立みどりの学園義務教育学校に学ぶ〜/中村 めぐみ・黒上 晴夫
ワークショップ
【7月30日(午前・午後)】
【特別ワークショップ】★動画あり
カリキュラム・マネジメント推進における校長のリーダーシップ
/村川 雅弘・八釼 明美・石田 有記・渡部 淳子
ワークショップ
【7月30日(午前)】★動画あり
外国語デジタル教科書が与えるインパクトと日本型学校教育の未来
/池田 勝久
ワークショップ
【7月30日(午前)】★動画あり
情報モラル教育で行う「深い学び」につなげる合意形成の協働学習
/榎本 竜二
ワークショップ
【7月30日(午前)】
NHK for Schoolを活用した授業と家庭学習のデザイン/宇治橋 祐之
ワークショップ
【7月30日(午前)】★動画あり
ひらめき体験教室の理論と実践~心理的手法と脳のメカニズム~
/鹿嶋 真弓
※午前・午後で同じ内容です。
ワークショップ
【7月30日(午後)】
試して実感!生成AIで変わる国語授業と先生の働き方/渡邉 光輝
ワークショップ
【7月30日(午後)】★動画あり
ネットに詳しくなくてもできるナッジ理論を使った情報モラル教育
/榎本 竜二
ワークショップ
【7月30日(午後)】★動画あり
情報活用能力を身に付け発揮する学び/西田 光昭
ワークショップ
【7月30日(午後)】★動画あり
ひらめき体験教室の理論と実践~心理的手法と脳のメカニズム~
/鹿嶋 真弓
※午前・午後で同じ内容です。

池田 修
肩書
京都橘大学 発達教育学部 教授
プロフィール
OECD,PISA問題作成委員、東京書籍「新しい国語」編集委員などを歴任。文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」学識経験者。学校教育DXアドバイザー。
講座
7月29日(火) ワークショップ:教育を豊かにするChatGPTを体験しよう
7月30日(水) 特別講演:生成AIが変える学校教育の姿

村川 雅弘
肩書
甲南女子大学人間科学部 教授
プロフィール
大阪大学助手、鳴門教育大学大学院准教授・教授等を経て現職。
研究開発学校企画評価委員など文科省関連委員多数。
『ワークショップ型教員研修 はじめの一歩』『子どもと教師の未来を拓く総合戦略55』等、著書多数。
講座
7月29日(火) 基調講演:「ICT活用力と自己調整力を育む授業とカリキュラム」
7月29日(火) 鼎談: 1単位40・45分午前5時間制による特色ある教育活動の実現・自己調整力の育成・働き方改革の推進
7月30日(水) 特別ワークショップ:カリキュラム・マネジメント推進における校長のリーダーシップ

黒上 晴夫
肩書
関西大学総合情報学部 教授
プロフィール
思考スキルおよびシンキングツールにフォーカスを整理・体系化するとともに、それらを活用した授業デザイン、探究的学習のカリキュラムやその評価方法について研究しつつ、さまざまな学校の実践研究を支援している。
講座
7月30日(水) 事例発表:DXの中で大事にしたいこと 〜つくば市立みどりの学園義務教育学校に学ぶ〜

中村 めぐみ
肩書
つくば市立みどりの学園義務教育学校 教頭
プロフィール
2017年・2019年度に東京書籍教育論文ICT部門で優秀賞を受賞し、つくば市のプログラミング必修化に尽力。みんなのコード第1期生としてプログラミング教育を推進。文科省の教育データ利活用有識者会議、GIGAスクール構想に関する各種委員や調査協力者会議の委員として活動し、1人1台端末の活用や校務の情報化を支援。
講座
7月30日(水) 事例発表:DXの中で大事にしたいこと 〜つくば市立みどりの学園義務教育学校に学ぶ〜

石川 仙太郎
肩書
文部科学省 総合教育政策局 教育人材政策課 教員免許・研修企画室長
プロフィール
〇平成30年1月 在マレーシア日本国大使館一等書記官
○令和3年4月 科学技術・学術政策局企画官
〇令和4年8月 秘書官(大臣)事務取扱
〇令和5年9月 総合教育政策局教育人材政策課教員免許・研修企画室長
講座
7月29日(火) 講演:「新たな教師の学びの姿」の実現に向けた仕組みの構築

宇治橋 祐之
肩書
NHK放送文化研究所 主任研究員
プロフィール
幼保向けから小中高等学校向けの各教科・領域の学校放送番組、教育情報番組・ドキュメンタリーなどを制作。
現在は教育とメディアに関する調査・研究を担当。全国各地で教員研修や大学のゲスト講師などを実施。
講座
7月30日(水) ワークショップ:NHK for Schoolを活用した授業と家庭学習のデザイン

榎本 竜二
肩書
元東京女子体育大学 准教授
プロフィール
システムエンジニアから都立学校の教員となり、東京都教育センターで専門教育主事、東京女子体育大学 准教授を経て聖心女子大学、中央大学等の非常勤講師を務めた。著書は高校教科書「情報Ⅰ」(東京書籍)等。
講座
7月30日(水) ワークショップ:情報モラル教育で行う「深い学び」につなげる合意形成の協働学習
7月30日(水) ワークショップ:ネットに詳しくなくてもできるナッジ理論を使った情報モラル教育

小林 玄
肩書
東京学芸大学 准教授
プロフィール
東京学芸大学にて学生支援センターと教職大学院を兼務。
教職課程科目を担当する傍ら、都内複数地域で学校巡回相談を務めた。
講座
7月29日(火) ワークショップ:通常の学級に在籍する要支援児①~長所活用型指導による支援~
7月29日(火) ワークショップ:通常の学級に在籍する要支援児②~心理的疑似体験による理解~

池田 勝久
肩書
文部科学省初等中等教育局 主任教科書調査官(外国語)
プロフィール
公立学校で約30年勤務後、私立小学校副校長及び愛知大学非常勤講師。H29より文部科学省。行政研修から校内研修まで各種研修(英語教育・デジタル教科書・カリマネ・授業改善・教員の意識改革等)を務める。
講座
7月30日(水) ワークショップ:外国語デジタル教科書が与えるインパクトと日本型学校教育の未来

鹿嶋 真弓
肩書
立正大学 心理学部臨床心理学科 教授
講座
7月30日(水) ワークショップ:ひらめき体験教室の理論と実践~心理的手法と脳のメカニズム~

渡邉 光輝
肩書
お茶の水女子大学附属中学校 教諭
プロフィール
千葉県生まれ。千葉大学大学院修了。千葉県の公立中学校教諭、千葉大学教育学部附属中学校教諭を経て、現職。表現教育、情報活用能力育成、メディアリテラシー教育、ICT活用を中心に研究・実践に取り組む。
講座
7月30日(水) ワークショップ:試して実感!生成AIで変わる国語授業と先生の働き方

矢野 充博
肩書
和歌山大学教育学部附属中学校 教諭
プロフィール
2006年から和歌山大学教育学部附属中学校に勤務。
著書:中学校ワクワク飛び出すARを使った理科授業
Apple Distinguished Educators, Class of 2015
講座
7月29日(火) ワークショップ:PBLで探究的な学び&ARの活用事例紹介と少し体験

西田 光昭
肩書
柏市教育委員会 教育研究専門アドバイザー
プロフィール
千葉県公立小学校教諭、千葉県柏市教育委員会指導主事、千葉県公立学校教頭、校長を勤め、2017年4月より、柏市教育委員会教育専門アドバイザー、文部科学省学校DX戦略アドバイザー、日本教育工学協会(JAET)理事。
講座
7月30日(水) ワークショップ:情報活用能力を身に付け発揮する学び

村川 弘城
肩書
日本福祉大学 全学教育センター 講師
プロフィール
情報学(博士)。2017年1月に現センターへ異動。普段の生活の中で子どもたちが好きで育んでいる力を教育に活かすという視点から、ゲームに勝つための方略を考えることを教育に活かすことを中心に研究。
講座
7月29日(火) ワークショップ:トランプゲーム「大富豪(大貧民)」の戦略を考え、プログラミング的思考力を育もう
7月29日(火) ワークショップ:「深い学び」につなぐ手立てを探る〜コラボノートを活用して〜

石堂 裕
肩書
兵庫県たつの市立神部小学校 校長
プロフィール
兵庫県たつの市立神部小学校校長 大阪教育大学非常勤講師
県内外の教育センターや校内研修で,子どもを主体とした主体的・対話的な深い学びへの授業改善やカリキュラム・マネジメントなど支援を行う。
講座
7月29日(火) ワークショップ:「深い学び」につなぐ手立てを探る〜コラボノートを活用して〜

田部 久美子
肩書
千代田区立お茶の水小学校 主任教諭
プロフィール
教育ジャーナル」(Gakken) 特別座談会「社会に開かれた学び」情報活用能力×学校教育
前編:情報活用能力の育成を踏まえた学びとは、後編:情報活用能力の育成~課題と展望~。登壇
講座
7月29日(火) ワークショップ:生成AIの活用による校務の効率化と授業改善

久保 賢太郎
肩書
玉川大学教育学部教育学科 講師
プロフィール
1988年北海道札幌市生まれ。玉川大学教育学部教育学科講師。中野区立北原小学校教諭、東京学芸大学附属世田谷小学校教諭を経て、2024年より現職。
主たる研究テーマは、遊戯概念を手がかりにした学習環境デザイン、学習者及び教師の自己調整学習と知識構築。
著書に「褒めるは学びの落とし穴:子どもが輝く対話のメカニズム」など。
講座
7月29日(火) ワークショップ:学習者自身によるAARサイクルの駆動とICT機器活用

小寺 絢子
肩書
株式会社Grow-S 教室運営部教務リーダー
プロフィール
さくらんぼ教室・教室長としてわかりやすく楽しい学習・SST指導を実践し、現在は教務リーダーとしてカリキュラム・教材作成、人材育成などを担当。「発達が気になる子の『できる』をふやす国語」(Gakken)
講座
7月29日(火) 子どもの心とことばを育むコミュニケーションワークショップ~”プレ思春期”のソーシャルスキルトレーニング~

玉村 昌彦
肩書
目黒区教育委員会事務局 教育指導課 指導主事
プロフィール
・目黒区立中目黒小学校教務主幹(平成30年度〜令和3年度)
・目黒区教育委員会事務局教育指導課指導主事4年目
・東京都教育委員会研究開発委員(理科)
・目黒区授業スペシャリスト(理科)
講座
7月29日(火) 鼎談:1単位40・45分午前5時間制による特色ある教育活動の実現・自己調整力の育成・働き方改革の推進

相田 宜紀
肩書
滋賀県愛荘町立秦荘西小学校 教頭
プロフィール
令和5年度より現職。
柔軟な教育課程を導入し、そこに教科担任制・学年担任制を掛け合わせることで、児童によし、保護者によし、教員によしの「三方よし」の学校作りに取り組んでいる。
講座
7月29日(火) 鼎談:1単位40・45分午前5時間制による特色ある教育活動の実現・自己調整力の育成・働き方改革の推進

八釼 明美
肩書
知多市立新知小学校 校長
プロフィール
愛知教育大学卒業。愛知教育大学教職大学院修了。
愛知県岡崎市・知多地方教員を経て現職。『GIGA実現ハンドブック』等、著書多数。
「GIGAすごろく」やスタートカリキュラム作成支援ツール『サクスタ2』など教員支援ツールの作成を多数手掛ける。
講座
7月30日(水) 特別ワークショップ:カリキュラム・マネジメント推進における校長のリーダーシップ

石田 有記
肩書
日本体育大学 児童スポーツ教育学部 教授
プロフィール
平成11年文部省(現・文部科学省)入省後、教育課程、教員研修、教育財政等の職務を担当後、
行政官国内研究員、市川市教委教育次長、教育課程企画室長を経て、現職。
講座
7月30日(水) 特別ワークショップ:カリキュラム・マネジメント推進における校長のリーダーシップ

渡部 淳子
肩書
戸田市立新曽中学校 校長
プロフィール
令和2年度 戸田市立新曽中学校 教頭
令和3年度 戸田市立戸田中学校 教頭
令和4年度 戸田市立美笹中学校 教頭
令和5、6年度 戸田市立美笹中学校 校長
現 戸田市立新曽中学校 校長
講座
7月30日(水) 特別ワークショップ:カリキュラム・マネジメント推進における校長のリーダーシップ
対面
講習テーマ【基調講演】★動画あり
ICT活用力と自己調整力を育む授業とカリキュラム
/村川 雅弘
講師

村川 雅弘
肩書
甲南女子大学人間科学部 教授
プロフィール
大阪大学助手、鳴門教育大学大学院准教授・教授等を経て現職。研究開発学校企画評価委員など文科省関連委員多数。
『ワークショップ型教員研修 はじめの一歩』『子どもと教師の未来を拓く総合戦略55』等、著書多数。
講演概要
GIGAスクール構想の最終ゴールは、子ども自身がICTを活用して、自己のよさをさらに伸ばしたり、興味・関心を広げたり、弱点を補強したりできることである。
その際、同時に自己の学びや生活の目標を設定し、計画を立て、実践し、見直し・改善を図るマネジメント力(=子ども一人一人の自己のカリキュラム・マネジメント、自己調整力)を育成することが求められる。
その意義と具体的な取組を紹介する。
対面
講習テーマ【講演】
「新たな教師の学びの姿」の実現に向けた仕組みの構築
/石川 仙太郎
講師

石川 仙太郎
肩書
文部科学省 総合教育政策局 教育人材政策課 教員免許・研修企画室長
プロフィール
〇平成30年1月 在マレーシア日本国大使館一等書記官
○令和3年4月 科学技術・学術政策局企画官
〇令和4年8月 秘書官(大臣)事務取扱
〇令和4年9月 総合教育政策局教育人材政策課教員免許・研修企画室長
講演概要
教育公務員特例法の改正により、研修履歴の記録や資質能力の向上に関する指導助言等を行う仕組み(研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励)が制度化されました。本制度の効果的・効率的な運用のために構築された「全国教員研修プラットフォーム(Plant)」の概要や、令和5年12月の中央教育審議会諮問を踏まえた教師の質向上に関する考え方等について、説明します。
対面
講習テーマ【鼎談】★動画あり
1単位40・45分午前5時間制による特色ある教育活動の実現・自己調整力の育成・働き方改革の推進
/村川 雅弘・玉村 昌彦・相田 宜紀
講師

村川 雅弘

玉村 昌彦

相田 宜紀
肩書
○村川 雅弘:甲南女子大学 人間科学部 教授
○玉村 昌彦:目黒区教育委員会事務局 教育指導課 指導主事
○相田 宜紀:滋賀県愛荘町立秦荘西小学校 教頭
プロフィール
○村川 雅弘
大阪大学助手、鳴門教育大学大学院准教授・教授等を経て現職。研究開発学校企画評価委員など文科省関連委員多数。
『ワークショップ型教員研修 はじめの一歩』『子どもと教師の未来を拓く総合戦略55』等、著書多数。
○玉村 昌彦
・目黒区立中目黒小学校教務主幹(平成30年度〜令和3年度)
・目黒区教育委員会事務局教育指導課指導主事4年目
・東京都教育委員会研究開発委員(理科)
・目黒区授業スペシャリスト(理科)
○相田 宜紀
令和5年度より現職。
柔軟な教育課程を導入し、そこに教科担任制・学年担任制を掛け合わせることで、児童によし、保護者によし、教員によしの「三方よし」の学校作りに取り組んでいる。
講演概要
目黒区の全小学校と一部の中学校及び滋賀県愛荘町立秦荘西小学校は、文部科学省研究開発学校として、1単位40・45分午前5時間制に取り組んでいる。単元レベルで授業の工夫・改善を行うと共に、生み出された時間を活用し、各校が特色ある教育活動を展開したり、研修や教材研究の時間の確保等を行うことにより働き方改革にも寄与している。また、児童生徒が自ら生活や学習をマネジメントする力の育成にも着手している。目黒区教育委員会の玉村指導主事と秦西小の相田教頭から具体的な取組やその効果をお聞きし、検討・検証する。
対面
講習テーマ【7月29日(午前)】
教育を豊かにするChatGPTを体験しよう/池田 修
※午前・午後で同じ内容です。
講師

池田 修
肩書
京都橘大学 発達教育学部 教授
プロフィール
OECD,PISA問題作成委員、東京書籍「新しい国語」編集委員などを歴任。文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」学識経験者。学校教育DXアドバイザー。
ワークショップ概要
「ChatGPTという名前は聞いた事はあるけれども、Googleの検索とはどう違うの?」。基礎的なところから説明を始めます。また体験もします。かなり驚くと思います。
PC・タブレットを使用します。Wi-Fiの接続に不安のある方は、事務局から貸し出しますが、数に限りがありますのでご了承ください。
対面
講習テーマ【7月29日(午前)】★動画あり
PBLで探究的な学び&ARの活用事例紹介と少し体験
/矢野 充博
講師

矢野 充博
肩書
和歌山大学教育学部附属中学校 教諭
プロフィール
2006年から和歌山大学教育学部附属中学校に勤務。
著書:中学校ワクワク飛び出すARを使った理科授業
Apple Distinguished Educators, Class of 2015
・Yanoteaチャンネル(YouTube)
・理科の授業(Note)
ワークショップ概要
二つのテーマをお話しします。PBLでデジタル図鑑制作における探究的な学びと非認知能力との関係についてのお話、もう一つは、AR(拡張現実)の技術を使った理科の授業紹介とロイロノートを使ってARの体験、さらにはReality Composerを使ってARコンテンツの制作を少し体験していただきます。理科以外の教科でどのように活用できるかについてもみなさんとお話しします。
PC・タブレットを使用します。Wi-Fiの接続に不安のある方は、事務局から貸し出しますが、数に限りがありますのでご了承ください。
対面
講習テーマ【7月29日(午前)】★動画あり
トランプゲーム「大富豪(大貧民)」の戦略を考え、プログラミング的思考力を育もう/村川 弘城
講師

村川 弘城
肩書
日本福祉大学 全学教育センター 講師
プロフィール
情報学(博士)。2017年1月に現センターへ異動。普段の生活の中で子どもたちが好きで育んでいる力を教育に活かすという視点から、ゲームに勝つための方略を考えることを教育に活かすことを中心に研究。
・大富豪プログラミング
ワークショップ概要
トランプゲーム大富豪には、「最も弱いカードを出す」という基本的な出し方がありますが、あえて最も強いカードを出すという戦法を取ることがあります。
ここでは、この戦法を条件と行動に分けて伝えるという活動を通して、プログラミング的思考力を育むことを目指します。最終的にScratch上でプログラムすることを目指しますので、PCを持参していただけると嬉しいですが、複数人で1台でも可能です。
対面
講習テーマ【7月29日(午前)】
学習者自身によるAARサイクルの駆動とICT機器活用
/久保 賢太郎
講師

久保 賢太郎
肩書
玉川大学教育学部教育学科 講師
プロフィール
1988年北海道札幌市生まれ。玉川大学教育学部教育学科講師。中野区立北原小学校教諭、東京学芸大学附属世田谷小学校教諭を経て、2024年より現職。
主たる研究テーマは、遊戯概念を手がかりにした学習環境デザイン、学習者及び教師の自己調整学習と知識構築。
著書に「褒めるは学びの落とし穴:子どもが輝く対話のメカニズム」など。
ワークショップ概要
OECDによるEducation2030“Learning Compass”によれば、学習者自身が自ら見通しをもち、活動し、その振り返りから次の見通しを創出する“AARサイクル”が重要視されています。これからの学校教育においては、このAARサイクルを学習者自身が駆動する、そうした学びの実現が欠かせません。
そこで本ワークショップでは、学習者主体の学びにおける「振り返り」の重要性と指導のポイント、そして「ICT」機器活用についてみなさんと考えていきます。
対面
講習テーマ【7月29日(午前①・午後②)】
通常の学級に在籍する要支援児
① ~長所活用型指導による支援~
②~心理的疑似体験による理解~
/小林 玄
講師

小林 玄
肩書
東京学芸大学 准教授
プロフィール
東京学芸大学学生支援センター/教職大学院准教授。公認心理師、学校心理士SV、特別支援教育士SV。大学にて教職課程科目等を担当する傍ら、都内複数の地域で研修会講師や巡回相談員を務めてきた。
ワークショップ概要
学習面や行動面に困難さを抱える子どもは、その活動を「できる」か「できない」かで評価されがちである。しかし、その活動に至る処理の方略を変えれば、「できない」ことが「できる」ことに変わることがある。通常の学級に8.8%存在すると言われている要支援児を、その子どもが得意とする認知処理のスタイルを活用して支援していく方法について、具体的な事例を挙げて解説する。① ~長所活用型指導による支援~(午前) ②~心理的疑似体験による理解~(午後)
※こちらをご希望の方は、午後のワークショップの選択はできません。
対面
講習テーマ【7月29日(午後)】
教育を豊かにするChatGPTを体験しよう/池田 修
※午前・午後で同じ内容です。
講師

池田 修
肩書
京都橘大学 発達教育学部 教授
プロフィール
OECD,PISA問題作成委員、東京書籍「新しい国語」編集委員などを歴任。文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」学識経験者。学校教育DXアドバイザー。
ワークショップ概要
「ChatGPTという名前は聞いた事はあるけれども、Googleの検索とはどう違うの?」。基礎的なところから説明を始めます。また体験もします。かなり驚くと思います。
PC・タブレットを使用します。Wi-Fiの接続に不安のある方は、事務局から貸し出しますが、数に限りがありますのでご了承ください。
対面
講習テーマ【7月29日(午後)】★動画あり
「深い学び」につなぐ手立てを探る 〜コラボノートを活用して〜
/石堂 裕・村川 弘城
講師

石堂 裕

村川 弘城
肩書
○石堂 裕:兵庫県たつの市立神部小学校 校長
○村川 弘城:日本福祉大学 全学教育センター 講師
プロフィール
○石堂 裕:兵庫県たつの市立神部小学校校長 大阪教育大学非常勤講師
県内外の教育センターや校内研修で,子どもを主体とした主体的・対話的な深い学びへの授業改善やカリキュラム・マネジメントなど支援を行う。
○村川 弘城:情報学(博士)。2017年1月に現センターへ異動。普段の生活の中で子どもたちが好きで育んでいる力を教育に活かすという視点から、
ゲームに勝つための方略を考えることを教育に活かすことを中心に研究。
ワークショップ概要
コラボノートを活用した実践事例の報告に加え,石堂を先生役に模擬授業形式で,参加された先生方とともに,子どもたちの深い学びの実現に向けた授業づくりへの手立てを探っていきます。
なお,コラボノートの便利な使い方や新たな機能の紹介は,模擬授業の中で,体験していただく予定です。
PC・タブレットを使用します。Wi-Fiの接続に不安のある方は、事務局から貸し出しますが、数に限りがありますのでご了承ください。
○協力:JR四国ソリューション株式会社
対面
講習テーマ【7月29日(午後)】
生成AIの活用による校務の効率化と授業改善
/田部 久美子
講師

田部 久美子
肩書
千代田区立お茶の水小学校 主任教諭
プロフィール
教育ジャーナル」(Gakken) 特別座談会「社会に開かれた学び」情報活用能力×学校教育
前編:情報活用能力の育成を踏まえた学びとは、後編:情報活用能力の育成~課題と展望~。登壇
ワークショップ概要
「この仕事、AIがやってくれたらなぁ」と思うことはありませんか。生成AIは、想像以上に教師の仕事を楽にしてくれる機能を多くもっています。多岐にわたる校務や日々の授業改善に生成AIがどのように役立てられるのか。また、「心」と向き合う道徳科の授業に「心」をもたない生成AIがどこまで力を貸してくれるのかなど、簡単な実践とともに、ご参加の皆様と一緒に生成AIの活用法を考えたいと思います。
PC・タブレットを使用します。Wi-Fiの接続に不安のある方は、事務局から貸し出しますが、数に限りがありますのでご了承ください。
対面
講習テーマ【7月29日(午後)】★動画あり
子どもの心とことばを育むコミュニケーションワークショップ ~”プレ思春期”のソーシャルスキルトレーニング~/小寺 絢子
講師

小寺 絢子
肩書
株式会社Grow-S 教室運営部教務リーダー
プロフィール
さくらんぼ教室・教室長としてわかりやすく楽しい学習・SST指導を実践し、現在は教務リーダーとしてカリキュラム・教材作成、人材育成などを担当。
「発達が気になる子の『できる』をふやす国語」(Gakken)
・さくらんぼ教室
・さくらんぼ教室メソッド『プレ思春期のSST』ワーク
ワークショップ概要
「コミュニケーション」は楽しい学校生活のキーワード。複雑な感情と出会う思春期の子どもたちに、自分の気持ちや考えをことばで伝え分かち合う経験をしてほしい。
本ワークショップは学習塾で実践する「ソーシャルスキルトレーニング」からコミュニケーション指導のコツをお伝えし、子どもとの対話力、共感力を高める活動を体験をしていただきます。
(参考:さくらんぼ教室メソッド『プレ思春期のSST』ワーク/Gakken)
対面
講習テーマ【特別講演】★動画あり
生成AIが変える学校教育の姿
/池田 修
講師

池田 修
肩書
京都橘大学 発達教育学部 教授
プロフィール
OECD,PISA問題作成委員、東京書籍「新しい国語」編集委員などを歴任。文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」学識経験者。学校教育DXアドバイザー。
講演概要
生成AIは、今までの学校教育の姿を根底から変える可能性があります。学習者主体、個別最適化、自由進度などと、生成AIはとても相性が良いのです。また、教員の業務改善にも劇的な寄与をします。講演では実際にライブでお見せします。デバイスを用意してご参加いただければ、その場で試して頂くことも可能です。
対面
講習テーマ【講演】
データから見る子どもの学びと将来イメージ/川田 夏子
講師
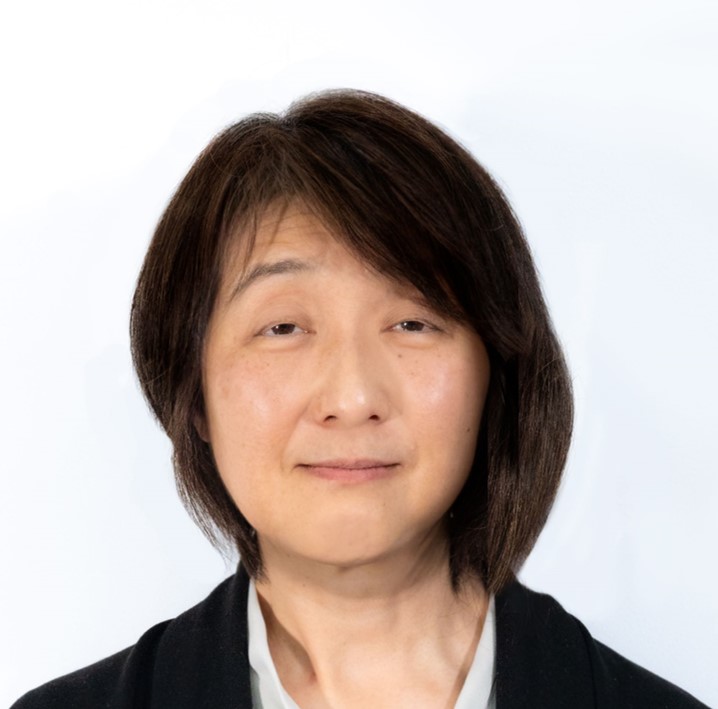
川田 夏子
肩書
学研ホールディングス 学研教育総合研究所 所長
プロフィール
1988年㈱学習研究社(現学研ホールディングス)に入社。㈱学研プラス(現㈱Gakken)等で、1年~6年の『学習』編集長、幼児・児童書籍部門の事業部長、学研プラスほかグループ内事業会社4社の取締役兼任を経て、2022年より現職。
講演概要
社会の急速な変化に伴い、子どもたちのキャリア観・将来像も多様化し始めています。こうした状況の中で、子どもたちがより豊かな人生を送るために、大人はどうしたらよいか? 子どもたちは何を考えているのか?「小学生・中学生・高校生白書 2024」の調査から見えてきた、その現在地をお伝えします。
対面
講習テーマ【事例発表】★動画あり
DXの中で大事にしたいこと 〜つくば市立みどりの学園義務教育学校に学ぶ〜/中村 めぐみ・黒上 晴夫
講師

中村 めぐみ

-進行- 黒上 晴夫
肩書
〇中村 めぐみ:つくば市立みどりの学園義務教育学校 教頭
〇黒上 晴夫:関西大学総合情報学部 教授
プロフィール
〇中村 めぐみ:2017年・2019年度に東京書籍教育論文ICT部門で優秀賞を受賞し、つくば市のプログラミング必修化に尽力。みんなのコード第1期生としてプログラミング教育を推進。文科省の教育データ利活用有識者会議、GIGAスクール構想に関する各種委員や調査協力者会議の委員として活動し、1人1台端末の活用や校務の情報化を支援。
〇黒上 晴夫:思考スキルおよびシンキングツールにフォーカスを整理・体系化するとともに、それらを活用した授業デザイン、探究的学習のカリキュラムやその評価方法について研究しつつ、さまざまな学校の実践研究を支援している。
講演概要
みどりの学園義務教育学校は、2040年代のチェンジメーカーを育てる次世代の学びを実現するとともに、子供だけでなく先生にとっても幸せな学校づくりを目指しています。
次世代の学びの実現は、デジタル学習基盤といわれる先進的ICT環境の中で、子供たちが主体的、探究的に学ぶための素地をどのように育てていくかや、生成AIを授業だけでなく校務においてもよりよく活用することへの挑戦をご紹介します。
紹介動画
対面
講習テーマ【7月30日(午前・午後)】
【特別ワークショップ】★動画あり
カリキュラム・マネジメント推進における校長のリーダーシップ
/村川 雅弘・八釼 明美・石田 有記・渡部 淳子
講師

村川 雅弘

八釼 明美

石田 有記

渡部 淳子
肩書
〇村川 雅弘:甲南女子大学 教授
〇八釼 明美:知多市立新知小学校 校長
〇石田 有記:日本体育大学 児童スポーツ教育学部 教授
○渡部 淳子:戸田市立新曽中学校 校長
プロフィール
〇村川 雅弘:大阪大学助手、鳴門教育大学大学院准教授・教授等を経て現職。研究開発学校企画評価委員など文科省関連委員多数。
『ワークショップ型教員研修 はじめの一歩』『子どもと教師の未来を拓く総合戦略55』等、著書多数。
〇八釼 明美:愛知教育大学卒業。愛知教育大学教職大学院修了。
愛知県岡崎市・知多地方教員を経て現職。『GIGA実現ハンドブック』等、著書多数。
「GIGAすごろく」やスタートカリキュラム作成支援ツール『サクスタ2』など教員支援ツールの作成を多数手掛ける。
〇石田 有記:平成11年文部省(現・文部科学省)入省後、教育課程、教員研修、教育財政等の職務を担当後、
行政官国内研究員、市川市教委教育次長、教育課程企画室長を経て、本年4月より現職。
○渡部 淳子:令和2年度 戸田市立新曽中学校 教頭
令和3年度 戸田市立戸田中学校 教頭
令和4年度 戸田市立美笹中学校 教頭
令和5、6年度 戸田市立美笹中学校 校長
現 戸田市立新曽中学校 校長
特別ワークショップ概要
これまで生徒指導困難校や学力面で厳しい学校にかかわり、カリキュラム・マネジメントで立て直してきました。カリマネはコロナ禍やGIGAスクール構想など様々な教育課題にも有効な考え方です。カリマネに関する講話や事例紹介、カリマネを推進してきた元文科省幹部とカリマネで学校経営を展開している校長との鼎談を踏まえて、カリマネを推進していくための年間通しての具体的な戦略を協働的に練り上げるワークショップです。
※午前・午後のセットになり、こちらをご希望の方は午後のワークショップの選択はできません。
対面
講習テーマ【7月30日(午前)】★動画あり
外国語デジタル教科書が与えるインパクトと日本型学校教育の未来
/池田 勝久
講師

池田 勝久
肩書
文部科学省初等中等教育局 主任教科書調査官(外国語)
プロフィール
公立学校で約30年勤務後、私立小学校副校長及び愛知大学非常勤講師。H29より文部科学省。行政研修から校内研修まで各種研修(英語教育・デジタル教科書・カリマネ・授業改善・教員の意識改革等)を務める。
ワークショップ概要
第2次GIGAスクール構想がスタートし、デジタル教科書がどんな意味を持つのかを「令和の日本型学校教育」「個別最適な学び」「協働的な学び」といったキーワードを使って説明する。
また、デジタル教科書を外国語へ優先的に無償給与している背景を伝え、これからの外国語教育のあり方、機械翻訳や生成AIなどのテクノロジーとどう向き合っていけばよいのか、さらに、これからの教師に求められる資質・能力について議論したい。
対面
講習テーマ【7月30日(午前)】★動画あり
情報モラル教育で行う「深い学び」につなげる合意形成の協働学習
/榎本 竜二
講師

榎本 竜二
肩書
元東京女子体育大学 准教授
プロフィール
システムエンジニアから都立学校の教員となり、東京都教育センターで専門教育主事、東京女子体育大学 准教授を経て聖心女子大学、中央大学等の非常勤講師を務めた。著書は高校教科書「情報Ⅰ」(東京書籍)等多数。
ネット社会の歩き方
ワークショップ概要
協働学習と言いながらも教師が仕切った「ただの顔合わせ」や「結論が見え見えの話し合い」になっていませんか。各班の結論をクラスで共有するだけでは学習になっていません。
協働学習に本当に大切なことは、参加メンバー全員が「合意(コンセンサス)」することであり、そこから確かな自信や新たな気づきにつながります。
ここでは、ゲーム化した教材を使うことで合意形成をするプロセスを実際に体験します。
対面
講習テーマ【7月30日(午前)】
NHK for Schoolを活用した授業と家庭学習のデザイン/宇治橋 祐之
講師

宇治橋 祐之
肩書
NHK放送文化研究所 主任研究員
プロフィール
幼保向けから小中高等学校向けの各教科・領域の学校放送番組、教育情報番組・ドキュメンタリーなどを制作。
現在は教育とメディアに関する調査・研究を担当。全国各地で教員研修や大学のゲスト講師などを実施。
NHK for School
ワークショップ概要
小中学校の学年・教科に対応した90シリーズ、2100本に及ぶ番組、そして知識定着や調べ学習をサポートする7000本の動画クリップ。
全国の教育現場で利用されているNHK for Schoolを、一人一台端末を活用して、授業と家庭学習でどう連携させてデザインすればよいのか。
全国のさまざまな事例もみながら考えていく。
対面
講習テーマ【7月30日(午前)】★動画あり
ひらめき体験教室の理論と実践~心理的手法と脳のメカニズム~
/鹿嶋 真弓
※午前・午後で同じ内容です。
講師

鹿嶋 真弓
肩書
立正大学 心理学部臨床心理学科 教授
プロフィール
高知大学教育学部准教授、高知大学教職大学院教授を経て2019年3月より現職。
・TILA教育研究所
ワークショップ概要
『ひらめき体験教室』とは、主体的対話的で深い学びを実現するための準備体操として考案されたものです。
ひらめき体験教室のナゾを解くには「話す」「試す」「間違いを恐れない」ことが必要で、それを繰り返していくうちにグループ内の知的交流が自然と生まれてきます。
人間の脳のメカニズム、わからないとモヤモヤし、わかったらスッキリする体験こそが、もともと誰にでもあった「不思議センサー」の磨き直しにつながるのです。
対面
講習テーマ【7月30日(午後)】
試して実感!生成AIで変わる国語授業と先生の働き方/渡邉 光輝
講師

渡邉 光輝
肩書
お茶の水女子大学附属中学校 教諭
プロフィール
千葉県生まれ。千葉大学大学院修了。千葉県の公立中学校教諭、千葉大学教育学部附属中学校教諭を経て、現職。表現教育、情報活用能力育成、メディアリテラシー教育、ICT活用を中心に研究・実践に取り組む。
・生成AIがひらく国語教室の未来
ワークショップ概要
生成AIの活用によって、国語の授業は、校務はどのように変わるのか?本ワークショップでは、実際の活用事例を紹介しながら、参加者自身が生成AIを操作し、授業づくりや校務の効率化を体験します。
教材作成や思考を深める課題の設計など、国語科ならではの活用法を一緒に探究しましょう。
AIを活用することで生まれる新たな学びの可能性と、先生の働き方改革を実感できる実践的なワークショップです。
PC・タブレットを使用します。Wi-Fiの接続に不安のある方は、事務局から貸し出しますが、数に限りがありますのでご了承ください。
対面
講習テーマ【7月30日(午後)】★動画あり
ネットに詳しくなくてもできるナッジ理論を使った情報モラル教育
/榎本 竜二
講師

榎本 竜二
肩書
元東京女子体育大学 准教授
プロフィール
システムエンジニアから都立学校の教員となり、東京都教育センターで専門教育主事、東京女子体育大学 准教授を経て聖心女子大学、中央大学等の非常勤講師を務めた。著書は高校教科書「情報Ⅰ」(東京書籍)等。
ネット社会の歩き方
ワークショップ概要
デジタルシティズンシップで指摘されるまでもなく,ネットどころか校内に関しても禁止や強制が溢れています。鞭や飴では人は動かないのです。だから情報モラルが進みません。
行動の禁止や強制ではなく,優しくするべきことを後押し促す戦略・手法をとることをナッジ理論と呼びます。このナッジ理論とはどのようなもので何の役に立つのかを具体的に説明し,実際に校内やネット上の困りごとに当てはめて作っていきます。
対面
講習テーマ【7月30日(午後)】★動画あり
情報活用能力を身に付け発揮する学び/西田 光昭
講師

西田 光昭
肩書
柏市教育委員会 教育研究専門アドバイザー
プロフィール
千葉県公立小学校教諭、千葉県柏市教育委員会指導主事、千葉県公立学校教頭、校長を勤め、2017年4月より、柏市教育委員会教育専門アドバイザー、文部科学省学校DX戦略アドバイザー、日本教育工学協会(JAET)理事。
ワークショップ概要
「各教科等の特質に応じて適切な学習場面で育成を図り、育まれた情報活用 能力を発揮させることにより,各教科等における主体的・対話的で深い学び へとつながっていく」とされる、学びの基盤となる情報活用能力について理解を深め、情報を読み取り、比較整理し、まとめて伝える、情報活用能力を育成する場面、発揮する場面をどのように作っていくのか演習を通じて考えます。
○協力:日本教育工学協会(JAET)
受講者の皆様へ
ご自身のタブレット端末等をご持参ください。
用意できない方は、台数に限りはございますが、事務局でタブレット端末の貸し出しをいたします。
対面
講習テーマ【7月30日(午後)】★動画あり
ひらめき体験教室の理論と実践~心理的手法と脳のメカニズム~
/鹿嶋 真弓
※午前・午後で同じ内容です。
講師

鹿嶋 真弓
肩書
立正大学 心理学部臨床心理学科 教授
プロフィール
高知大学教育学部准教授、高知大学教職大学院教授を経て2019年3月より現職。
・TILA教育研究所
ワークショップ概要
『ひらめき体験教室』とは、主体的対話的で深い学びを実現するための準備体操として考案されたものです。
ひらめき体験教室のナゾを解くには「話す」「試す」「間違いを恐れない」ことが必要で、それを繰り返していくうちにグループ内の知的交流が自然と生まれてきます。
人間の脳のメカニズム、わからないとモヤモヤし、わかったらスッキリする体験こそが、もともと誰にでもあった「不思議センサー」の磨き直しにつながるのです。
アーカイブ
講習テーマアーカイブの詳細は未定です。
講師