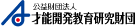ABOUT
才コンについて
あなたの作品をコンテストに応募しませんか?
全国児童才能開発コンテストは昭和38年に制定され、以来毎年行われている顕彰事業です。
図画部門、作文部門では、学校を通して応募を受け付けており、

-

作文部門とは
作文を通して、自分の思いや願いを文章で表現する力を育みます。
-

図画部門とは
感性や想像力を働かせながら、自分の思いを絵に表現することを狙いとしています。
-

科学部門とは
科学への興味・関心を深め、物事に対する知的好奇心を育みます。
毎年たくさんの作品を応募いただいています
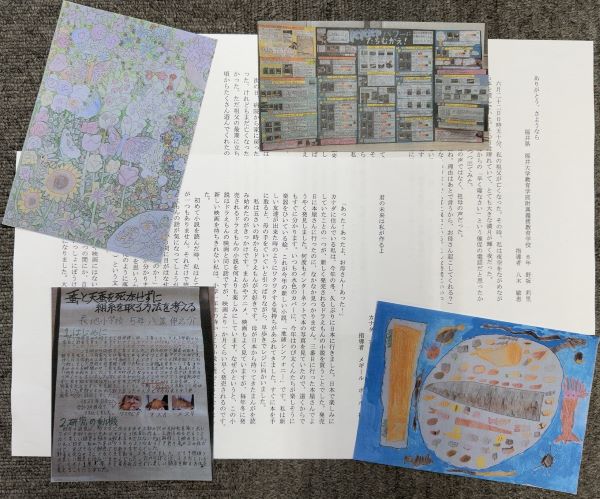
こんな風に審査しています
令和6年度(第61回)審査会レポート
作文部門
令和6年度(第61回)受賞作品
審査の経過


総評 文部科学省教科調査官 大塚 健太郎
本年度も全国児童才能開発コンテストにおいて、すばらしい数多くの作品が集まりました。日頃の学習の成果を生かし作品を仕上げようとしている姿に、嬉しく思います。最終審査に集まった作品のテーマは実に様々で、子供たちの生活が豊かに広がっていることを感じることができました。
審査の段階で出合った低学年の作品には、型にはまった表現ではなく小さい事柄に対してものびやかに書かれている作品が多く見られました。また、高学年の作品には、扱うテーマについても主張する考えについてもこちらがはっとさせられるものも多く、読者に自分の思いの強さや考えの鋭さなどを効果的に伝える構成や表現の工夫がなされているものが多い印象でした。
さて、世の中では、コンピュータを使うと、あたかも自分の考えであるかのように文章がまとまる時代となっています。そんな時代だからこそ、実際に体験して、自分の頭で考えたり、心で感じたりして、そしてなにより自分の言葉を大切にして作品にまとめられた皆さんの挑戦は素晴らしいものです。今回も適切な文章になるように、頭の中にあるたくさんの言葉から紡ぎだしたり何度も推敲したりして、自分の思いや考えにぴったりくる言葉が見つかった時にはうれしくなったのではないでしょうか。人の心を動かす作品をまとめるにはたくさんの力が必要です。これからも、一回書いたものを直す、整理する、見つめなおすなど、読み直して描写を加えたり、始まりを工夫したり、ちょっとした表現の工夫を取り入れたりして、社会に思いや考えを発信し続けほしいと思います。
最後なりましたが、支えてくださった保護者の皆様、指導くださった教職員の皆様、コンクールに関わられた皆様に感謝を申し上げます。
図画部門
令和6年度(第61回)受賞作品
審査の経過


総評 文部科学省教科調査官 小林 恭代
今年も全国児童才能開発コンテストで、たくさんの作品に出会うことができました。審査員の先生方と、一枚一枚の絵を丁寧に、どんな思いで表したのか想像しながらじっくりと見させていただきました。
今、生成AIが話題になっています。いくつかの指示を入力すると、絵を描いてくれるものもあり、本物そっくりな絵があっという間にできるのです。とても便利になったと思うと同時に、では、人が絵を描く意味はなんだろうと、改めて考えさせられます。
絵に表すことを通して、皆さんは様々な力を身に付けています。例えば、自然の美しさに感動したり、人とのふれあいに温かさを感じたりするなど、さまざまなものや出来事を心に感じ取る力。「こうなったらいいな」「こんなことをしてみたいな」と、夢や願いをもち、豊かに想像する力。自分が表したいことを見付け、どうやって表していくか考える力。表したいことに合わせて材料や用具を使う力や、表し方を工夫して表す力。うまくいかないときでもあきらめず、粘り強く最後までやりきる力などです。コンピューターは、体がありませんから、実際の経験から感じることはできません。自分の思いをもとに表現することは、人間だからできること、そして心豊かなことでもあるのです。今回、作品に表そうと挑戦した皆さんには、きっとその力が付いていっていると思います。どうぞ、これからも、自分らしさを大切にし、絵に表すことを楽しんでください。
先生方、保護者の皆様には、子供が様々な思いをもっていることを心に留め、あたたかく見守っていただいていることと思います。絵に表すことは、子供にとって未知への冒険であり、ワクワクすることでもあります。子供の表現を見守り、共感していくことは、子供の挑戦を支え、勇気付けることになるでしょう。これからも、一人一人の子供が、自分の思いを大切にして絵に表す活動を進めることができるよう、その子供らしい表現を励まし、支えていただきますようお願いいたします。
科学部門
令和6年度(第61回)受賞作品
審査の経過


総評 中部大学卓越教授 黒田玲子
今年度のコンテストにも、例年と同様に多数の優れた作品の応募がありました。本当に嬉しいことで、審査員一同わくわくしつつもじっくりと審査にあたりました。
各作品は、子供が学校の学習で体得した知識などをベースに、科学的なものの見方・考え方の広がりと深まりの過程を、工夫をこらしながら記録したものといえます。今回、最終審査に残った各学年3点、計18点のさまざまなテーマの研究作品は、次のような観点で審査されました。
●子供の発達段階相応の題材や内容、考え方で研究されているか。
●科学的な手法で研究が深まりをもっているか。また、継続研究の場合、方向性や進展性は適切かどうか。
昨今、人類への脅威となるさまざまな自然災害や感染症などへの対策が急務となっています。また、宇宙開発などの競争も激しくなっています。そのため、多分野での新たな科学的な研究や知見がますます求められていくことでしょう。当コンテストの審査に長年参加していますと、研究熱心な子供がとても多いことに感心させられます。さらに多くの子供が科学への興味・関心を深めてくれることを期待します。